神出とは
兵庫県神戸市西区に、神出町という地域があります。
読み方は、「かんで」。
神が出た町 と書くので、何があったんだろうとワクワクしますよね!
今回は、そんな神出町の地名に関する伝説をご紹介します。
突然ですが、私は神戸の小学校に通っていました。
他の地域はどうなのかわからないですが、社会科のテキストに「地図帳」と呼ばれるものがありました。
中身はすっかり忘れていて、神戸の地理などが書かれてたんだろうなと思いますが、「おっこさん、めっこさん(雄岡山、雌岡山)」の響きで盛り上がったことは、何故か記憶に深く刻まれています。
その、おっこさんめっこさんが、まさに神出町に位置します。
ほど近い距離に、低くなだらかな同じくらいの高さの山が二つ並ぶ姿から、様々ないわれがあるようですね。
でも今回は「神出」にフォーカスしているので、お山の話は写真だけに…。
(弁慶の盛られっぷり…)
地名の由来に関する伝説
形の良い山には、神が降りてくる伝説が残っていることが多いです。
めっこさんにもやはり伝説があり、これが「神出」という地名の由来になっています。
雌岡山にオオナムチ(大己貴命=大国主命)が降り立ち、百八十一柱の神々を生み落とされた。
それが基となり、この山の麓の里を神出と呼ぶようになった。という伝説が残っているそうです。
少しアレンジされた(?)パターンとして、めっこさん山上にある「神出神社」の石碑には、以下のようにあります。
神代に素盞嗚命(スサノオ)、奇稲田姫命(クシナダヒメ)の二神がこの雌岡山に降臨され
~中略~
二神の間に多くの神々がお生れになり、そのうち大己貴命はこの地でご生誕されたと言う。
このことからこの地を神出と言うようになった。という由緒書きがあります。
オオナムチはスサノオの子よりは孫のイメージの方が強いので、私としては後者は違和感ありますねー。
後日追記:日本書紀では孫ではなく息子だそうですね。不勉強でした!この裏には、時系列というか年代の調整・操作の影を感じますね…
でもどっちにしても、あのオオナムチがこの地に…。
そういえばもうすぐ旧暦10月、出雲の地に神々が集まる頃ですね。
めっこさん山上、「神出神社」
この前の記事でシェアサイクリングのレポートを投稿したのですが、この時の目的地であったのが「神出神社」です。
「神出神社」はめっこさん(雌岡山)の山上にあり、今回は自転車の都合もあり、通常の参道ではなく雌岡山梅林を抜けるルートで訪れました。
通常の参道ルートは割となだらかで歩きやすいようですが、こちらは勾配がすごいです。
暑い日は要注意です。
低く揃えられた梅林ごしに望むのどかな光景に、息を呑みます。
開花時期に再訪したいな。
急勾配を上がると…見えてきました
神出神社!このアングルかっこいい…
勾配を上がった分、景色は抜群です!
神戸を散策していると、ついつい覗きたくなる針の穴のオブジェを見ることがありませんか?
これは、神戸らしい眺望景観のあるスポットに設置される、「ビューポイントサイン」です。
神出神社にもあったんですね~!
この前に記事にした御影公会堂付近にもあったし、近日中にアップする保久良神社にもありました。
特に意識してないですが、ちょこちょこ出会う。
ところで、ばっちり中央に明石海峡大橋が…。
これは狙ったものなのか、あるいは、東経135度の関連を示唆しているのか…。
また、神戸に散在するビューポイントラインをGoogleMapで結ぶと…。
さらに、針の穴の指す方向は、それぞれある地点を収斂しており…。
全部ジョークですよ。
まあ実際、神出神社は東経135度線上といっても良いくらい接近してるんですけどね。
135度に反応しちゃうアナタは、立派な都市伝説好きです。
天王山でもある「雌岡山」
何かごちゃっとしちゃいますが、書いていたらちょっと思いついちゃったので、あとがき的な。
さっきも貼った写真ですが、御祭神は伝説とも一致する
- 素盞嗚命
- 奇稲田姫命
- 大己貴命
です。
おっこさんめっこさんは、かつて二山のとんがりが牛の角に例えられたことから、
男牛(おご)女牛(めご)と呼ばれ、やがて今の呼び名になったという説があるそうです。
牛の角…つまり牛の頭…牛頭天王…ときて、スサノオを祭るようになったのだったりして。
(牛頭天王はインド由来ですが、スサノオと同一視されています)
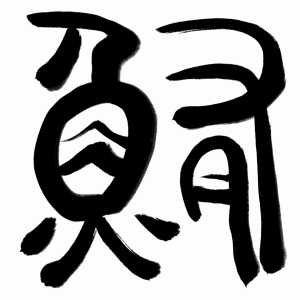
神戸に熱狂する人です。
神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。
神戸以外のネタもたまに。
カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。
内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。
ご連絡は、Twitterの方へ。
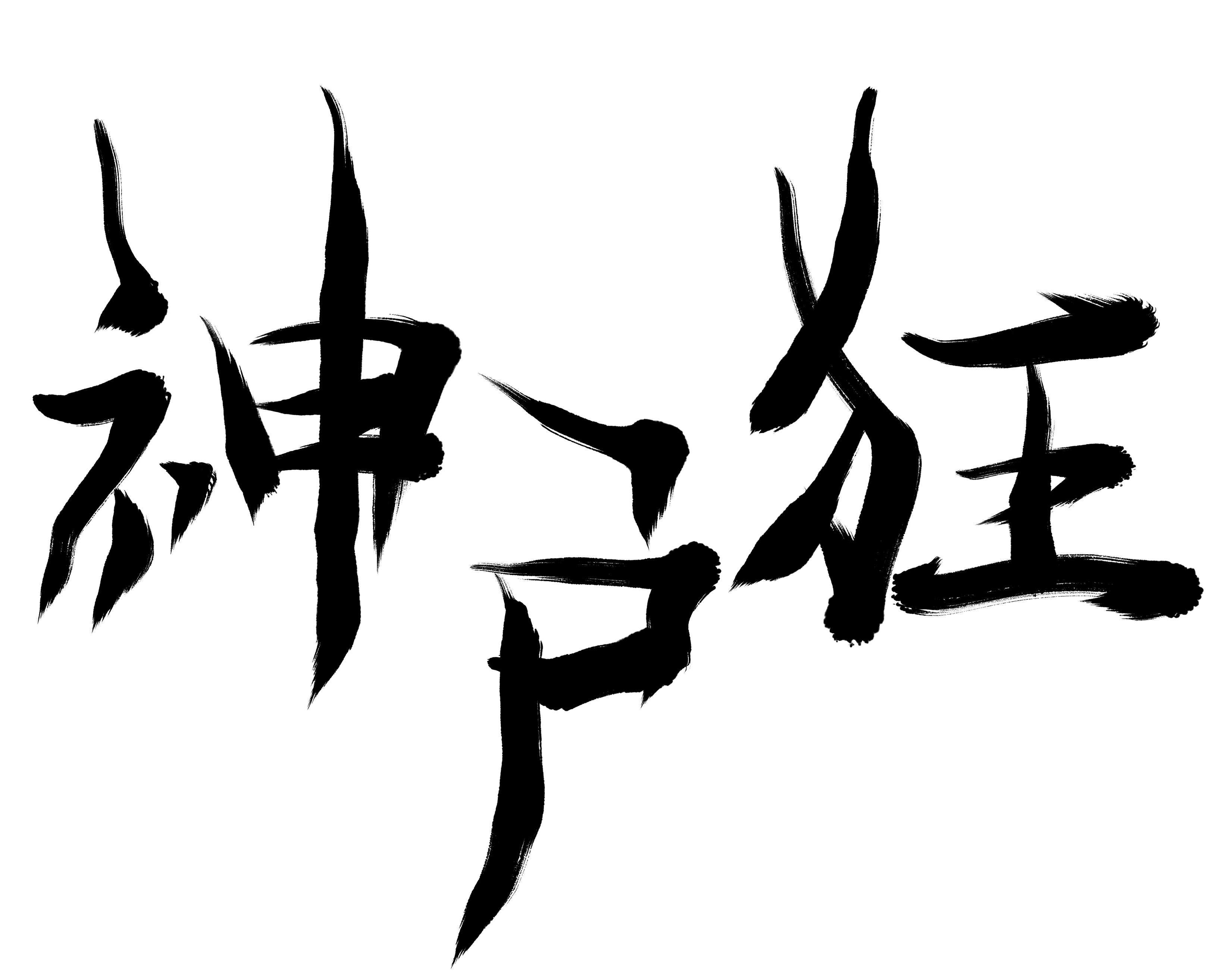












コメント