綱敷天満宮について
神戸には、名前に「綱敷」が付く神社が二つあります。
- 御影にある「綱敷天満神社」
- 須磨にある「綱敷天満宮
実はこの二社、同じ伝説を持っており、その由緒により名前が綱敷となっています。
そのため今回の記事では、どちらにも訪れてきました!
いずれも「天満宮」ということで、祀られているのは菅原道真となります。
菅公とか、天神さんと呼ばれたりもしますね。
言わずと知れた学問の神様であり、ほかにも神社巡りをされている方などは、「梅(梅紋)」「牛」などを見たらピーンと来るようになっておくと、ツウっぽいかもしれません!
菅原道真について
ご存知の方も多いかもしれませんが、ここでいったん神戸から離れ、菅公(菅原道真)が天神さまとして祀られるようになった経緯について触れておきます。
菅公は平安時代の貴族で、学者や官僚や詩人といった肩書を持つ、当時のスーパーインテリです。
時の宇多天皇に重用され、最終的には右大臣(朝廷のナンバー3)まで上り詰めたものの、学者上がりで重要ポジションに就いたことが貴族のヘイトを集め、政争に巻き込まれてしまうことに。
順調に出世し、後の醍醐天皇の世には右大臣として政を執る中、とうとう陰謀によって左遷されることとなってしまい、平安京(京都)から大宰府(福岡県)に移ることになりました。
移動は自費、左遷後もあらゆる圧力で、生活はかなり厳しいものだったとされており、左遷から二年後に非業の最期を遂げます……。
しかし菅公の死後、都では疫病や天災が続き、人々は菅公のたたりだと噂し始めました。
左遷の陰謀を企てたとされる人物も、若くして病死。
左遷を指示した醍醐天皇までも、宮中に落ちた雷をきっかけに崩御と、怨霊・道真の進撃は止みません。
そうした経緯で、今も京都にある「北野天満宮」に天神として祀られることとなりました。
菅公は人から怨霊、そして神へと雷により神成したのです。
「綱敷天満宮」という名前にまつわる伝説
こうした背景から、菅公が大宰府に渡る道中となった地には数々の伝説が残されています。
今回ご紹介する二社も、ともに菅公が立ち寄った地とされています。
それもなんと、名前の由来となったエピソードまでも丸被りなんです。
そんな、お互いどう評価し合っているんだろう?と勝手ながら気にしちゃう事情を、露わにしちゃいたいと思います。
大宰府へ渡る菅公一行は、
- 御影の沖合いに美しい松林を見つけ、船を着け上陸した。
- 荒波のために須磨に上陸した。
菅公をもてなすため集まった人々は、突然のことだったため、
石の上に綱をぐるぐると巻いて円座をつくり、そこに休憩してもらった。
その後の世で菅公が天神として祀られることになると、
"綱"を"敷"いて菅公をもてなしたゆかりの地として「綱敷」と呼ぶようになった。御影の綱敷天満神社
阪神石屋川駅から石屋川公園を北上するルート(オススメ)と、阪急御影駅から北西に下るルートがあります。
神社名としては「天満神社」となってるけど、神額には「天満宮」。
菅公あるあるその1:梅紋
菅公あるあるその2:牛
菅公あるあるその3:筆塚
須磨の綱敷天満宮
JR須磨駅から国道二号線を東に進むルートと、山陽電鉄須磨寺駅から北東に進むルートがあります。
が、神社周辺は史跡スポットがたくさんあるので、一緒に色々回ったついでがオススメです。
この日も色々回ったので、後日書いてみたいと思います。
(須磨寺、敦盛塚、村上帝社、琵琶塚、松風村雨堂…などなど)
なんと訪れた時は、改修中で本殿がよく見られず!
手水舎にハートが!
須磨らしさ!
鎮座1000年記念の三重塔!愛されてますね。
さいごに
なお御影の方のWEBサイトでは「菅原家の祖神・天穂日命が祀られる神社として、二度参拝されたゆかり深い地」
という由緒とされており、この地で綱を敷いたと明示はされてませんでした。
(菅公の像そばにある説明板には、ガッツリ書いてあるんですけどね)
……配慮?とか勘ぐってしまってゴメンナサイ!
あと実は訪れたのはずいぶんと前なのですが、記事を作りながら、再訪への想いがどんどん高まりました。
もちろん菅公の知識を入れたのもありますけど、梅の咲き誇る季節に行きたいなぁーって。
(保久良神社の時も言ってたな…)
あとね、御影の方は菅公像を撮るの忘れてたので、そのうち再訪して写真入れ替えておきます!
そして須磨の方は改修中だったので、そのうち再訪して写真入れ替えておきたいと思います!
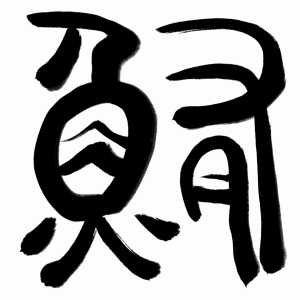
神戸に熱狂する人です。
神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。
神戸以外のネタもたまに。
カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。
内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。
ご連絡は、Twitterの方へ。
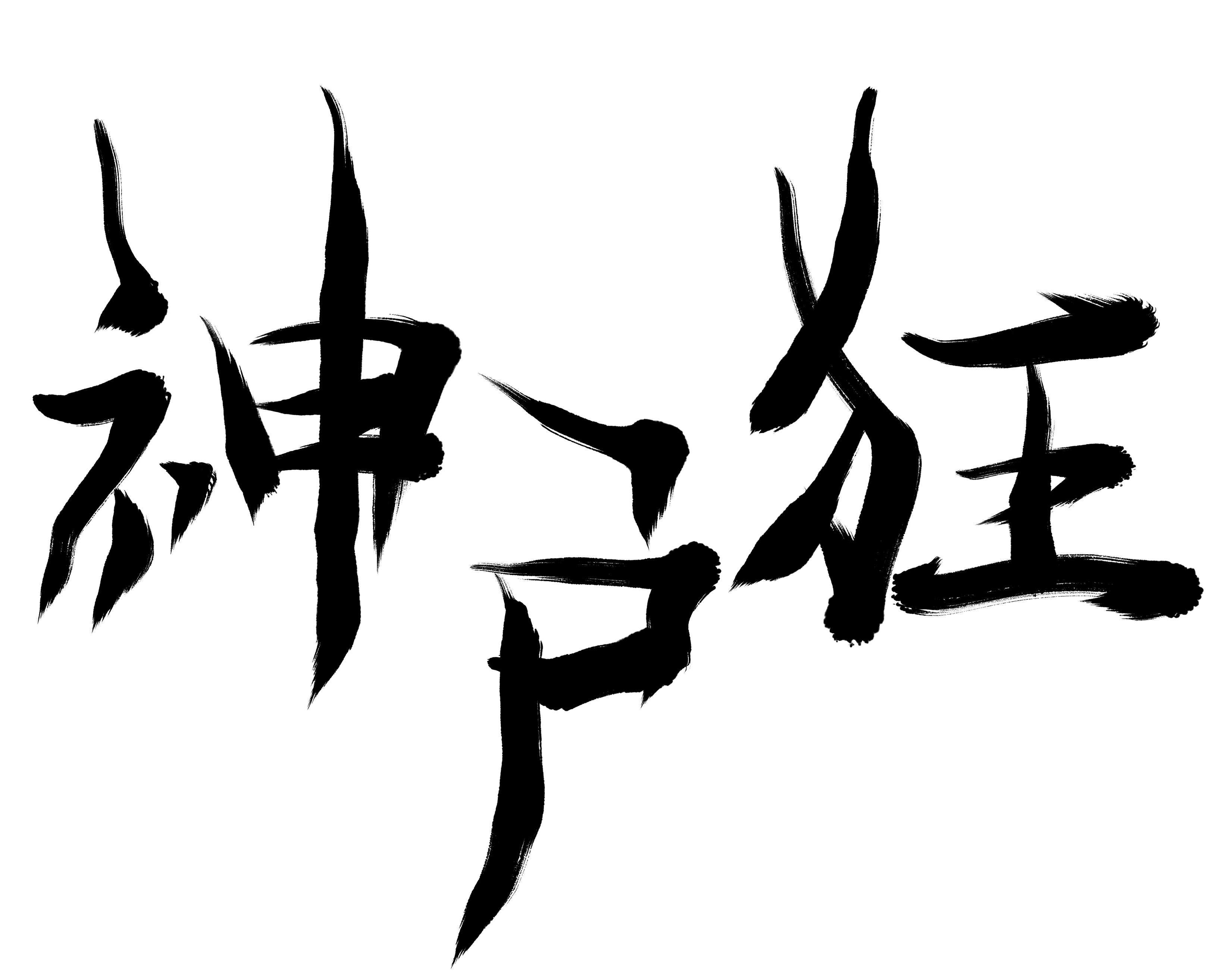

















コメント