割塚古墳について
「割塚古墳(わりづかこふん)」は、JR灘駅を北に出て線路沿いに西に進むとすぐにある、駅近古墳です。
といっても古墳自体は、豊臣秀吉の大阪城築城の際に材料とすべく取り壊されてしまったようで、今では石碑が立っているまでです。元々は横穴式石室の大円墳だったとのことです。
ちなみに、その石が割り取られていく様子から、割塚古墳という名前になったといわれているのだとか。
そんな、古墳としての形は失ってしまった割塚古墳ですが、実はロマン溢れる伝説が残っています。
今回は、割塚古墳の言い伝えを通し、神戸に眠る黄金伝説に触れていきます。
黄金が埋まっていた?割塚古墳
割塚古墳には、以下の様な言い伝えが残っています。
この塚には黄金千枚を埋めてあるので、筒井の里(割塚古墳があった地の呼び名)
が衰えたときには、掘り起こして村の復興に充てるように。果たして村の再興にどれほどの資金が必要かは判断つきませんが、相当な価値のお宝だったことはわかります。
仮に、いわゆる大判小判の大判が千枚だとどれくらいになるでしょうか。
昨今の金相場はだいぶ右肩上がりですが、本記事執筆時点(2023年6月25日)の最新相場では 9,746円/g と出ました。
大判は165gくらいだそうなので、その金額は…
165g × 9746円 × 1000枚 = 1,608,090,000円 → 16億809万円!!!
って今の貨幣価値で計算したところで実は大きな意味は持ちませんが、現代でも使いようで大きく化ける規模感だということは言えます。
誰が埋めた?そして誰が掘り起こした?というのが気になるところですね。
しかし、実のところ両方ともはっきりしていないみたいでした。
古墳の中の人からして、あまりはっきりしていないそうです。
ただ、石碑の裏側には「布敷首(ぬのしきのおびと)之霊地」と彫られており、確かではないものの、この方のお墓ということになっています。
埋められたタイミングも謎ですよね。
古墳が造られたのは7世紀頃とみられており、日本で金がみつかったのは少し後の奈良時代だそうです。
つまりこの頃に流通していた金は、舶来物となるわけですが、古墳築造当時に埋められたものなのか、はたまた以降の世に埋められたものなのか……。
神戸に残る黄金伝説
割塚古墳以外にも、神戸にはいくつかの黄金伝説があります。
- 長田にある御船の森(御船山)に埋められた黄金の船
- 六甲山上の石宝殿に埋められた黄金の鶏
- ヌノドの森の石祠に埋められた宝物と黄金の鶏
- 夢野にある宝塚
などなど
特に金鶏伝説は他にもいくつかあるようで、それぞれ「村の再興に使いなさい」という言い伝えがセットになっているようです。
なんというか……今の世にそのような言い伝えを残せば、我先にと向こう見ずに掘り起こした者が、一人で持ち逃げしてしまいまそうにしか思えません。
仮に埋めたとしても、私ならごくごく一部の信頼できる重要人物にしか伝えられないです。
しかし当時は、有事のための備えと扱ってくれることを信じ、言い伝えを広めた。
人々も、有事のための備えと語り継いできた……。
もちろん「謎を解き、黄金を掘りあてる!」みたいな方向の古代ロマンもわかる、というかそっち派ですが、
こういった黄金伝説が生まれること自体からも、当時の人々の考え方と現代のギャップを感じ、ロマンがあるなーと思いますね。
そして、私は黄金を掘り当てて一旗揚げたいので、下心満載に、黄金伝説の地を巡っていこうと決意したのでした。
割塚古墳への行き方
最初に書いた通り駅チカなのですが、一応通り道で撮影した写真を置いておきます。
駅の北側に出て、西に!
オシャなマンションを横目に、まっすぐ!
そしたら着く!
結構デカいです。
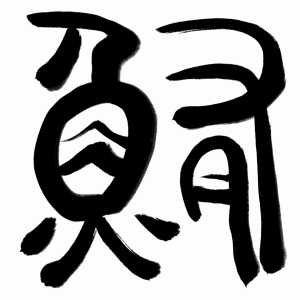
神戸に熱狂する人です。
神戸をより深く知るべく、歴史を知り、伝説の地を巡ったり、時にはオカルト的な都市伝説的なトピックも取り上げていきます。
神戸以外のネタもたまに。
カメラ持って歩くのが好きなので、普通に神戸の新しいトピックも上げます。
内容とは全く沿わない、ITエンジニアを本業としています。
ご連絡は、Twitterの方へ。
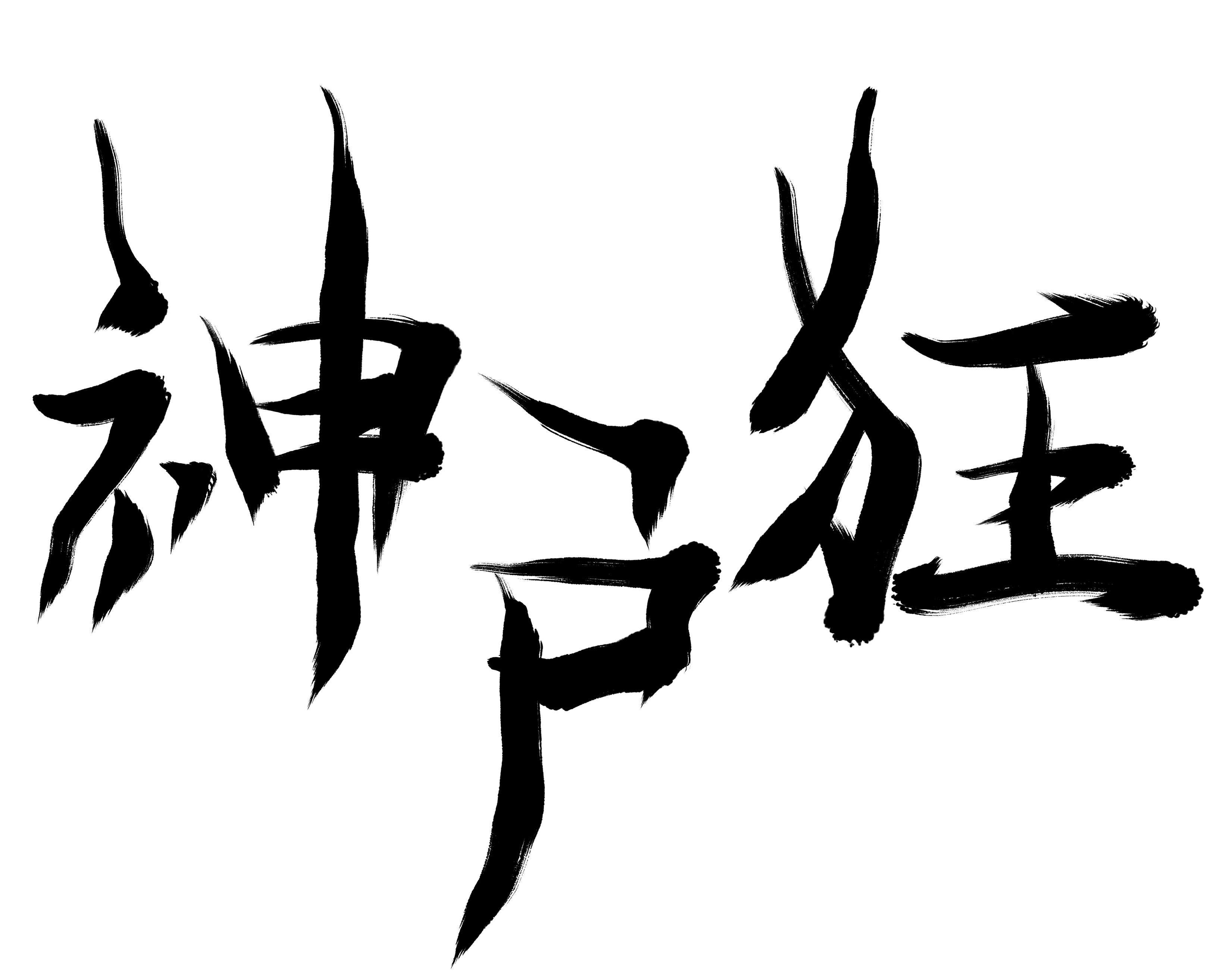









コメント